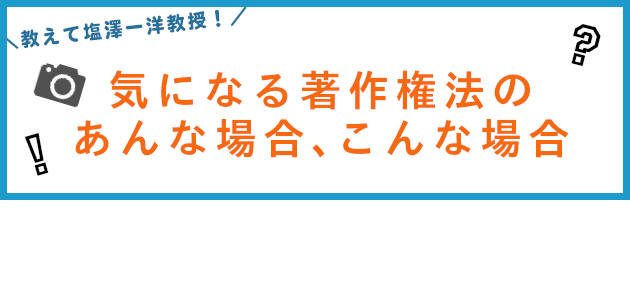写真家を志す人へ テラウチマサトの写真の教科書 第2回 私の修業時代
写真の学校を卒業したわけでもない、
著名な写真家の弟子でもなかったテラウチマサトが、
約30年間も写真家として広告や雑誌、また作品発表をして、
国内外で活動できているわけとは?
失敗から身に付けたサバイバル術や、これからのフォトグラファーに必要なこと、
日々の中で大切にしていることなど、
アシスタントに伝えたい内容を、月2回の特別エッセイでお届けします。
第1回 気が付いたら写真家になっていた
第2回 私の修業時代
第3回 9月18日(月)更新予定
第4回 10月2日(月)更新予定
テラウチマサト
写真家。1954 年富山県生まれ。出版社を経て1991 年に独立。これまで6,000人以上のポートレイトを撮影。ライフワークとして屋久島やタヒチ、ハワイなど南の島の撮影をする一方で、近年は独自の写真による映像表現と企業や商品、及び地方自治体の魅力を伝えるブランドプロデューサーとしても活動中。2012年パリ・ユネスコにて富士山作品を展示。主な写真集に、「ユネスコ イルドアクトギャラリー」でも展示した富士山をとらえた『F 見上げればいつも』や、NY でのスナップ写真をまとめた『NY 夢の距離』(いずれもT.I.P BOOKS)がある。www.terauchi.com
第2回 私の修業時代
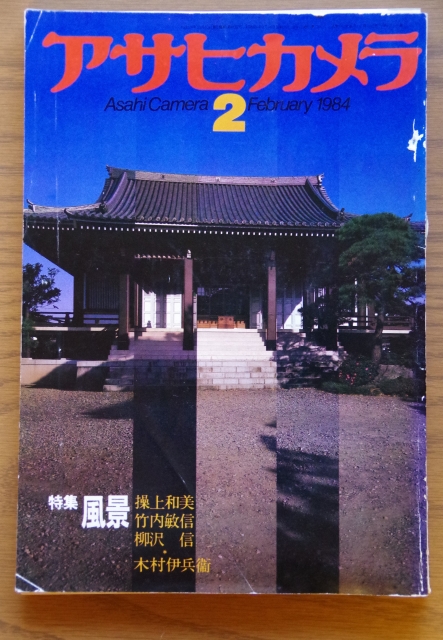
雑誌「アサヒカメラ」1984年2月号。フォトコンテストで2位を受賞した。その作品と当時の講評は、文の最後にご紹介しています。
写真家デビューは
「アサヒカメラ」の月例コンテスト!
「初恋は2度ある」と言われる。その説に同意する私だが、写真を始めた“あの頃”にも思い当たる何度かの“あの頃”がある。
最初にカメラを持って被写体を追いかけたのは小学校4年生。家族新聞と言う名の壁新聞をつくって、毎週タンスに家族新聞を貼り、記事に添えるための写真を撮っていた。使っていたカメラは、ハーフサイズカメラ(24枚撮りで48枚撮れた)で、バカでも撮れると評判のカメラ。クラスの友達から家族や街角、飼っていた金魚や田んぼで見つけた亀などを撮っていた。
2度目の“あの頃”は出版社に入り、編集部に籍を置きながら写真をやりたくてセミナーや写真教室に通い出した頃。さまざまなコンテストに応募する日々。最初に応募した写真は奈良公園で撮った芝生の上で腕立てをするカップル。コダックのポジフィルムとトライXというモノクロフィルムで撮った。カメラはキヤノンのAE-1だった。なかなかいい写真だったと思っているが、少し画面に対して主役が小さかったとも思う。その後「アサヒカメラ」の月例コンテストで2位を貰ったことをきっかけに、大小いろいろなコンテストに応募し入選を繰り返すようになった。そんなことがきっかけで、編集部長に認められ念願の写真部へと移籍。写真記者として歩み始めた。それが3度目の“あの頃”で、僕の本当の初恋みたいなものだ。
何度も怒られた写真部の日々
「芸は盗め」と言われるが一緒に機材を持ってついていき傍でやり方を見ているうちにライティングや4×5や中判カメラの扱い方は自然と覚えた。機材運びをメインに、傍にいてフィルム交換みたいなことだけだからボーッとしていたことも多かったのだろう。2人だけのときは雷のごとく怒鳴られたし、クライアントやADやその他関係者がいるときには「ちょっとエレベーターに行こう」と言われて乗ったとたん殴られたこともある。エレベーターは誰にも知られずお仕置きを受ける場所だった。一度「エレベーターに行こう!」と言われて、眼鏡を外しエレベーターが停まるのを待っていたら、「何をしている?」と聞かれ、素直に「殴られる準備を!」と答えたら、「今日はいい!」と許してもらったことがある。以来、エレベーターに呼ばれるとメガネを外して待つようになった。怒鳴られたり、ときにパンチも飛んできたが、写真部の日々は楽しかった。出張許可を申請したとき、「125分の1秒や60分の1秒とかで撮れるカメラでなぜ1泊するんだ」と本気か冗談か分からない責められ方をされたことも覚えている。
私の修業時代。カメラと共に生き始めた頃。写真部は熱い思いを持つメンバーが揃っていたし、撮影となると時間も気にせず無茶も無謀もやった。そんな組織程、冷静に数字を見られるリーダーが必要だったのだろう。人や仕事に対するウォームハートと数字に対するクールヘッド、この2つが両輪になるということを「125分の1秒…」の言葉で教わっていたのだといまになって気づかされる。
「夜明け前の砂漠を旅するような写真ですが、よく見ると、場所は海に面した波止場です。太陽が輝いている日中に、絞れるだけ絞り込み、空の調子を落としてわずかに青さを残し、金属の反射を利用してメカニックな部分を強調したため、超現実的な情景に、うまく作りかえられました。その点で、メカニックな現代に力強く生き抜くための心情を託した作者のねらいは成功です。ただ、現実性を欠いたポスター的な弱みはまぬがれません」
(雑誌「アサヒカメラ」1984年2月号より)
これから写真家になる!という決意を込めた「START」というタイトル、またこのときから名前はカタカナ表記にしていた。この写真をスタートにしてプロ写真家へと進むという気持ちだった。用意周到な応募で見事2位だったが、講評は辛口だ。