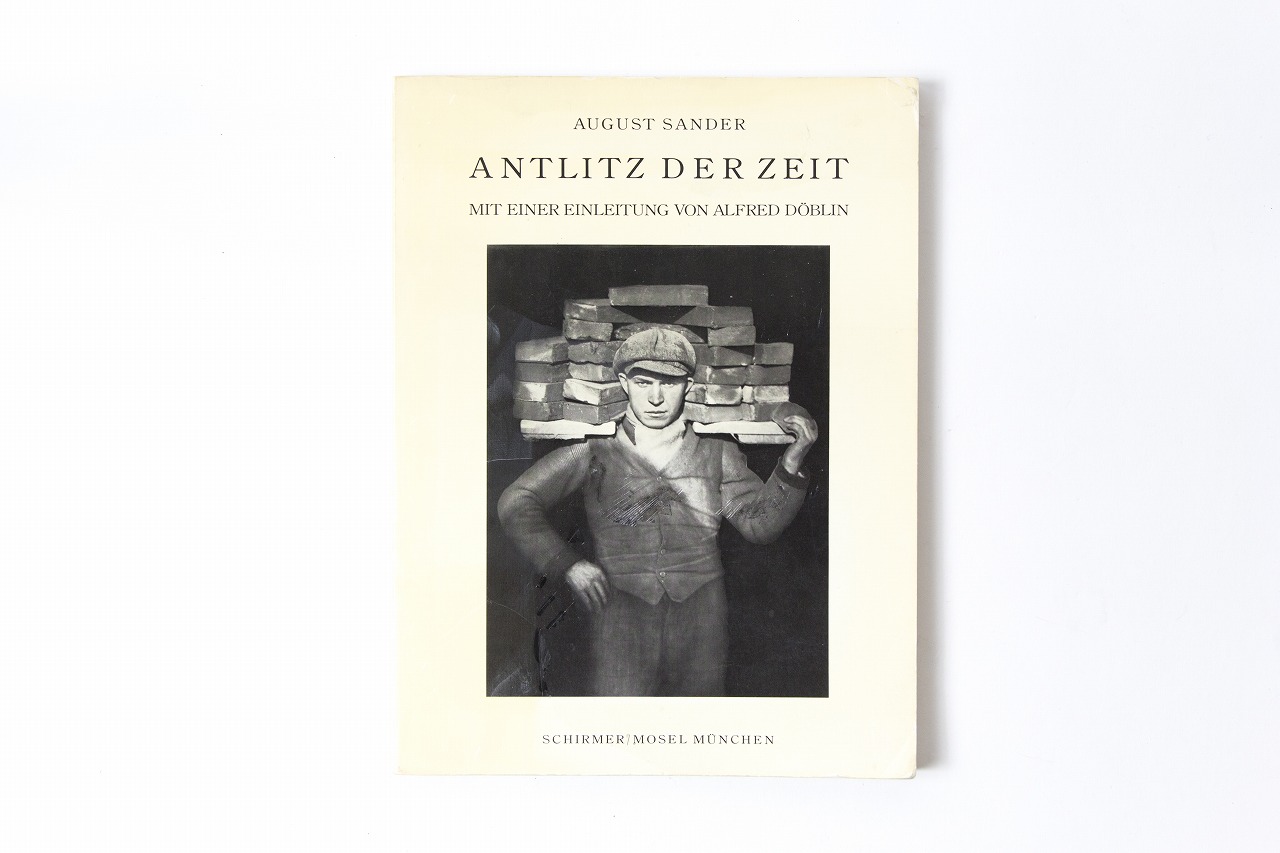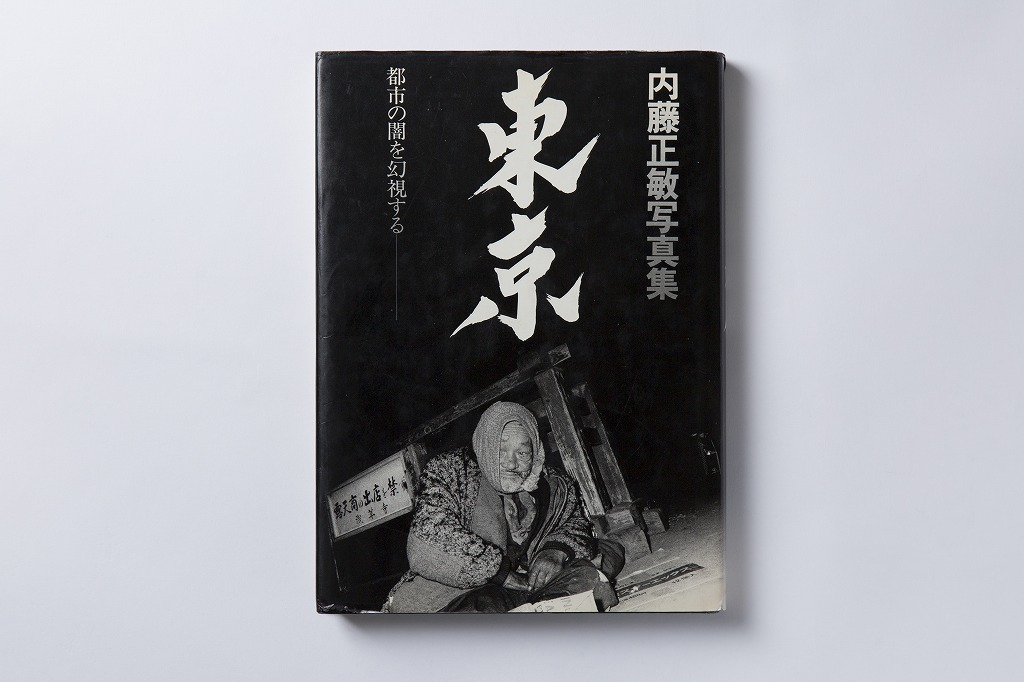下町生まれの木村伊兵衛が写した、ニューカラーの先駆といえるパリ写真|飯沢耕太郎が選ぶ時代に残る写真集

木村伊兵衛は1901年、東京市下谷区(現・東京都台東区)に生まれた。1924年、東京日暮里で写真館を開業。1930年、手持ちの機材を売り払ってドイツ製のライカを購入、花王石鹸に嘱託として入社し、広告写真を撮影しはじめる。1932年、野島康三、中山岩太と写真雑誌『光画』の創刊に同人として参加。
1933年、名取洋之助らと日本工房を結成して、報道写真に本格的に取り組むようになる。戦後は、日本写真家協会(JPS)の会長を長く務めるなど、写真界の重鎮として活動した。
木村伊兵衛は1954年9月2日にヨーロッパに旅立った。来日したマグナムのヴェルナー・ビショフ、ロバート・キャパに強く勧められたのがきっかけだった。当時は日本人の渡航制限があったが、日本光学(現・ニコン)が貿易促進のための顧問として派遣することを決定し、『アサヒカメラ』のための取材も決まった。
モノクロ主流の中で模索された数少ないカラー表現

木村はこの時に、モノクロームフィルム100本に加えて、富士写真フイルムから提供された「富士カラーフイルム」50本を持っていくことにした。
1949年に、同社初の外式リバーサルフィルムとして発売された「富士カラーフイルム」は、ASA(ISO)感度が昼光で10ほどだったが、派手な色味のコダック製カラーフィルムと比較して、「パステルカラーのような色彩」に特徴があった。
木村は戦前からカラー写真に強い関心を抱いており、ヨーロッパ外遊をきっかけに、その表現の可能性を探ろうとしていたのではないだろうか。
ブレッソンやドアノーから刺激を受け、撮った写真


ギリシャ、イタリア、ドイツなどを経て10月10日にパリに到着した木村は、アンリ・カルティエ=ブレッソンやロベール・ドアノーを紹介され、彼らとの対話からも刺激を受けて、水を得た魚のようにパリの街と人を撮り続けた。
4ヵ月余りのヨーロッパの旅の成果は、『アサヒカメラ』掲載後に『木村伊兵衛外遊写真集』(朝日新聞社、1955年)として刊行された。木村は1955年6月~9月にもヘルシンキ世界平和大会への出席を依頼されたのをきっかけに、ふたたびヨーロッパに滞在している。
この時も「富士カラーフイルム」で撮影を続け、写真集『ヨーロッパの印象 第2回外遊写真集』(朝日新聞社、1956年)を刊行した。
柔らかな眼差しでとらえたパリの街と人々


本書では、1954年、55年、さらに1960年の3度目の渡欧に際して撮影されたカラー写真を集成している。木村のパリのカラー写真は、『木村伊兵衛写真集 パリ』(のら社、1974年)に最初にまとまるが、本書はその全貌を再検討し、詳細な解説を加えた決定版というべき写真集である。

いかにも木村らしい柔らかな眼差しで、パリの街とそこに生きる人々をいきいきととらえた写真が並ぶ。色だけでなく、ヴィヴィッドな空気感を定着できるカラー写真の特性が、見事に活かされている。
写真家たちが作品制作にカラー写真を本格的に使いはじめるのは、1970年代後半に「ニュー・カラー」の潮流が形をとってから後になる。木村のパリの写真は、その先駆と位置づけられるだろう。


木村伊兵衛『木村伊兵衛のパリ』朝日新聞社、2006年
この記事を読んだあなたにおすすめ
ロバート・フランクが再び写真へ向かうきっかけに。突然訪ねてきた日本人と作った写真集とは?|飯沢耕太郎が選ぶ時代に残る写真集